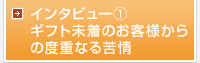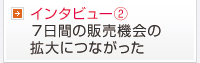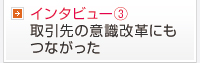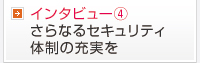「Web2000」導入事例インタビュー
導入事例インタビュー概要
| 業種 | 百貨店 |
|---|---|
| 参加者 | 食品バイヤーA、食品バイヤーB、顧客政策担当、業務推進担当 |
都内新宿区にある某百貨店。ギフトシーズンともなると全国から様々な問い合せが絶えず、猫の手も借りたいほどの忙しさで、スタッフ総出で日々対応しています。しかし、これはサンリッチ社のギフトオペレーションシステム「Web2000」を導入する以前の話。 システムを導入してからというもの、これまでのようなお客様からのギフト未着の苦情の嵐から一転、今では販売機会の拡大のみならず、取引先の意識まで変わりました。今回、某百貨店のギフト関係者に集まってもらい、システム導入までの一部始終と導入後の効果について本音で語っていただきました。
ギフト未着のお客様からの度重なる苦情
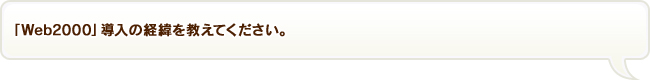

サンリッチさんが提案をくださった時期、われわれの百貨店では、複数部門が関わりギフトプロジェクトを実施していました。プロジェクトを進める中で、物流システムの導入も検討していたので、システム提案を受けた時は、こんなシステムが欲しかった!と思いました。
サンリッチさんは物流部、我々のような商品部など、いろんなセクションに提案をしていました。
百貨店の場合、各部署の役割と業務がはっきり分かれているので、新しくシステムを導入しようとしても、各部署それぞれにメリットがあるものでなければ会社からの決済は下りません。おそらく部署単位で個別に提案を受け続けても、部署の担当者はどう動いてよいか分からず、時間が過ぎるだけだったと思います。
要するに、決済ができないんです。こちらは、商品のことはわかるので、これは効果があると決済できても、物流のことは決済できない。だから部署横断的なプロジェクトが進行中だったということもあり、会社からの決済がスムーズに下りました。
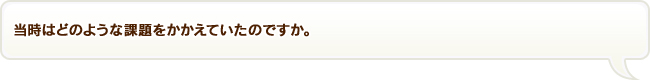

産直の物流フローが複雑だったというのが、もともと問題視していたことです。取り扱い方法や時間が業者ごとに異なっていて、そこがシステム化できていないという課題がありました。結局、担当者の熟練技でなんとか運用していました。
さらに課題に感じていたことは、お客様に対するサービスを向上させることができないということです。たとえば産直商品の注文を受けると一度商品センターで配伝したものをさらに現地に送ることで、二重にリードタイムがかかってしまい、一般商品と比べると商品到着までに時間を要してしまいます。今は、産直の場合、配送業者A社がほとんどですが、当社の場合、B社と包括契約をしているので、そこでたまに伝票が入れ替わってしまうことがあります。そうなると、お客様から未着の問合せがあったときにすぐには答えられないんです。どの伝票と入れ替わったのかと、いちいち確認をしているうちに丸一日かかってしまって余計にお客様を怒らせてしまうという結果になります。
それから、われわれ自身も配送完了を確認できないという課題がありました。もちろん取引先との信頼をベースにビジネスをしているのですが、「本当に送ったの?」ですとか、「ないから持ち帰ってそのまま報告をしていないんじゃない?」などという互いに疑いをかけるようなやり取りもありました。
ですので、配完情報を把握するために自社でシステムを開発するか、それともサンリッチさんの「Web2000」のように、すでに出来上がっているシステムを導入して運用していくのか、どちらかの選択肢がありました。
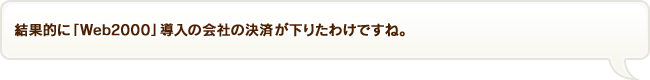

そうですね。さきほど言いましたように各部署が関係する、つまり複数部門を動かすというのは、結局経費が問題なんです。システムを入れるとしたら、イニシャルコストやランニングコストがいくらかかるのか?という経費の面が、一番の焦点です。あとは物流にかかわる費用です。細かいところで言いますと、配達記録の郵送料や伝票の現地に送る郵送料、複写式の伝票を作る経費、人件費など諸々です。
結局のところ、全体でどれくらいのコストが削減できて、時間が短縮するのか。さらに将来的に考えて何年後に回収できるのかを証明できないと、会社側としても承認がとれないわけです。
導入してからは、各部署がかかえている課題が解消できて、経費としても数年後に回収できて、利益が出る見通しがたっています。